翌日、放課後の部活の後、俺は学食裏のベンチに座っていた。
そう古くないはずだが、雨ざらしで所々、赤黒い地金がむき出しになっている。学食以外でも屋外で食事できるようにとテーブルとベンチを設置したそうだが、明らかに失敗している。すぐ近くに廃材置場があるような裏庭で一体誰が好き好んで食事を……いや、あいつらなら来そうだな。
特に恭介なんかは「うぉ、なんじゃこりゃぁー! はは、見ろよ、何かよく分からんとしか言いようがない謎の物体があるぞ!」とか何とか言って、はしゃぎそうだ。真人なら「おぉ! この重量感……やべぇ、これで鍛えた日にゃあ、俺の筋肉は更なる高みに突入しちまうぜ!」とか。そして、そこで鈴が「こいつ馬鹿だ!」といつものようにツッコミを入れて、最後に理樹が「いやいや、真人、それゴミだから。部屋に持ち込まないでね」とたしなめるんじゃないだろうか。
しばらく、そんな馬鹿なことを考えて、時間を潰していた。
古式へは弓道部の主将を通じて、時間と場所を伝えた。直接、別のクラスへ赴いて古式に伝えるのは気が引けた。どういうわけか俺は女に騒がれる。明け透けに言えば……モテる、と言えばいいのだろうが、そういう言い方は自意識過剰な気がして嫌だ。
世の中ではそういう状況を羨んだり、妬んだりする奴がいるが、俺には全く理解できない。表面的な所だけ見られて騒がれることの何が良いのだろうか。少なくとも、剣の道を往く俺には煩わしいだけだ。もし、俺が直接、古式の所へ行けば、そういった煩わしいことが更に煩わしくなるに違いない。俺だけが面倒なことになるならまだしも、それはおそらく古式にも及ぶだろう。そうなれば、古式の力になるどころか、害を齎してしまっただけになってしまう。
「……ふぅ」
今、何分ほど経ったのだろうだろうか? 時計もないので分からない。だが、取り決めた時間は過ぎていることだけは間違いない。古式が来ないなら来ないで良かった。それは赤の他人に過ぎない俺の力など必要としていない、ということなのだから。とりあえず、日が暮れたら帰るつもりだった。それは小学生だった頃、俺達リトルバスターズは日が暮れれば、解散していたことに起因しているかもしれない。
「……何時まで、そうしてるつもりなんですか」
暗く沈んだ声がした。閉じていた目を開くと、古式が沈みかかった夕陽を背に受けて立っていた。
「とりあえず、日が暮れるまでと決めていた」
「新人戦も近いのに……随分、暇なんですね」
「そうでもない。瞑想するのに忙しかったさ」
俺なりにギャグをかましたつもりだったが、古式はクスリともしなかった。……修行不足だな。
「“力になる”とのことですが、どういうことですか?」
「どういうことも何もそのままの意味だ。俺のできることはないか? 何でも力になる」
「何故そんなことするんですか? 宮沢さんに何か得があるわけでもないでしょう?」
「別に何かを見返りを求めているわけじゃない。言ってみれば、川で溺れた人を見かけたのと大して変わらん。自分が泳ぎが得意だったり、あるいは、たまたまロープなどを持っていたとしたら……真っ当な人間なら助けようと思うだろ? それと同じことだ」
後、追記するなら……俺には誇るべき友がいる。そして、できるなら俺もまた誇れるだけの良き友でありたいと思う。言ってみれば、これはその一環だとも言える。って、口にしてみるとすさまじく偽善的だな。
「尤も、力になるといっても、今できることと言えば、相談に乗るくらいしかできないが……とりあえず、座ったらどうだ? その方が楽だろう?」
「……失礼します」
一言告げて、古式が隣に座る。当然、寄り添うほど近い所ではなく、人一人分離れた所に。
「一つ、聞いてもいいですか……?」
「ああ、勿論。俺はそのためにここにいる」
「もし、剣を振るえなくなったとしたら……宮沢さんはどうしますか?」
「遊ぶだろうな」
予想していた質問だったので、然程間を置かずに答えた。
「遊び……ですか?」
「あぁ、遊びだ。仲間と馬鹿みたいに騒いで楽しむ。それでまず、剣への執着を笑い飛ばすだろうな。毎日そんな感じに過ごしながら、自分に何ができるか、何がしたいのか改めてゆっくり考えるだろうな……」
古式の件を受けて、まず考えたことは、もし、俺が剣を失ったらどうするだろうかということだった。古式が聞きたいことがあるとすれば、そこしかないように思えたからだ。そうでなければ、古式がわざわざ赤の他人である俺に相談する意味がない。
「古式も楽しいと思うことをすればいい。趣味とかはないのか?」
「趣味はありません。言ってみれば、弓道が趣味みたいなものでしたから……」
古式が視線を地面に落とす。
「宮沢さんはどうなんですか? 剣道以外に趣味は持っているんですか?」
「俺も……特に無いな。しいて言えば、仲間と遊ぶのが趣味みたいなものだろうか」
思えば、剣道以外の時間は殆どリトルバスターズの面々と過ごしている。理由は簡単だった。そこへ行けば、楽しいことが確実に待っているからだ。ならば、わざわざ趣味を持つ意味がなかった。
「……宮沢さんには、とても良いお友達がいらっしゃるんですね」
「古式にはいないのか。気が置けない親友は?」
「友達はいます。でも、特別仲の良いとなると、全員弓道部で……」
「そう、か……」
それだけで大体の事情は察することができた。
今は四月下旬。クラス替えが済んで、もうすぐ一か月になるか否かと言った所だ。既にグループの形成は終わっている。弓道の道が断たれた彼女が、加われる輪はないということだ。それも彼女の行動次第だと思うが、それは病み人に健康づくりのためにジョギングを勧めるようなものだ。そんな勇気は湧かないだろう。
かと言って、弓道部の友人と遊ぶなんてことは論外だ。腫れ物を触るような態度を取られるかも知れんし、もしそうでない者がいたとしても、弓道に関わる者が傍にいれば、どうあっても弓が引けない不公平感を考えずにはいられないだろう。結局、弓の呪縛からは逃れられない。
「それに私はずっと小さい頃から弓ばかり引いてきましたから……。クラスの女子の話題についていけないことも今まで結構ありました。芸能人の話とか、ファッション誌のこととか、テレビドラマの話とか……そういうこと全然分かりませんし、興味も無いんです。普通の女子が興味持ってそうなことは何も」
考えてみれば、真人以下の馬鹿なアドバイスをしてしまったんじゃないのか、俺は。
仲間と遊んで剣道のことを忘れる? 馬鹿か。それはそんなものがあるから言えることだ。そもそも、ずっと剣道に打ち込んでいた俺に、あいつらみたいな剣道とは無関係な……しかも、子供の頃からの親友がいること自体が奇跡みたいなものじゃないか。
古式からしてみれば、俺の意見は単なる自慢話くらいにしか聞こえなかっただろう。
「……すまない」
「何がですか?」
「いや、こちらの話だ」
俺は再び考え込んでいた。彼女に必要なのは、弓道に代わる新たな生き甲斐なのだろう。それは分かっている。しかし、俺には何も思いつかなかった。
「いつも……今、何のために生きてるのか。そればかり考えてしまうんです。学校がある日はまだマシな方で、でも放課後になるとまた考えだしちゃうんです。自宅通いの子たちが楽しそうに寄り道の話をしながら教室を去っていくのを見ながら、私一人寮に帰って……。弓道ができなくなると急に時間ができてしまって、でも、何かしないと変なことばかり考えちゃいますから、机に向かうんです。その日の宿題が終わったら、授業の復習をして、それも終わると今度は予習。全部終わると、もう何もすることが無くなって……ベッドに寝転がって夕食までジッとしてるんです。私も思ってるんですよ。このままじゃいけないなって。だから、色々考えるんですけど……ジッとしてると、時計の針の音がすごく大きく聞こえるんです。カッチカッチって、それが何だか急かされてるみたいで……」
古式は俺が考えてる以上に重篤だった。彼女は生き甲斐を、己が己であるための証左を失っただけじゃない。加えて――孤独だ。まるで免疫力を失くした患者でも見ているような気分だった。ちょっとした風邪でも肺炎になり、傷を作れば簡単に化膿してしまう。どうしようもないほど弱々しいそんな印象。
それは……初めて顔を合わせたあの日の理樹と似ていた。今の古式は心の抵抗力が著しく低下している。普段なら、どうと言うことはない他人の言葉でも簡単に傷ついてしまうんじゃないのか……?
「弓が引けなくなって良かったことは、どんな教科の小テストも満点が取れるようになったことでしょうか」
古式は屈みこみ、足元に落ちていた小石を拾った。そして、立ち上がって歩いて離れていく。数歩離れるとこちらを向いた。長い黒髪が遅れるように振り乱れる。
「宮沢さん、丸めたティッシュとか空き缶とかをゴミ箱に投げ捨てたりしたことありますか? 実は私、弓道以外でも百発百中だったんですよ、あれ。でも、今は……」
ベンチの近くに備え付けられたゴミ箱に向かって、古式は小石を投げた。小石は緩やかな放物線を描いて……。
カコンッ
ゴミ箱の下の部分に当たって、地面に落ちた。距離感が合ってなかった。
「ほら、入らないんです。――全然……入らなくなっちゃいました。情けないですよね、こんなに近いのに……こんな、近いのに」
顔を伏せて、肩を震わせ始めた古式に、俺は何も言うことができなかった。
日はもう落ちていて、夕闇が世界を覆っていた。直に夜が来る。今日の星はどのくらい輝いているのだろう。今日、月は満月だろうか。せめて、新月でなければいいのだが……。
少しでいい。明かりだけは絶やさないで欲しい。
ふと、そんなことを考えた。
「で? 俺の元に来たってわけか?」
「あぁ、何かアドバイスを頼む」
「んなこと言われてもなぁ。俺だってどうしたらいいか、さっぱり分かんねぇよ」
恭介は困ったように頭を掻いた。
結局、何一つ力になれなかった俺は、古式の後姿を見届けた後、その足で恭介の部屋を目指した。あまり人に聞かれていい相談ではなかったので、ルームメイトの先輩には退室してもらった。両肩に手をやりながら、「お願いします」と頼み込むと快く退室してくれた。しかし、あの先輩は肩でも凝っているのだろうか? 「イテテ」とか言いながら、やたらと肩を回していたが……今度会ったら、マッサージでもしてやるべきだろうか。
「う〜む、古式には趣味はないのか? 弓道がダメなら、趣味に打ち込んだらどうだ?」
「残念ながら趣味はないらしい。というか、すでにそれは俺が聞いた。もっとこう他に……“弓道の代わりになるような生き甲斐”はないのか?」
「いや、ズバリそのものを聞かれても逆に俺が困る」
恭介でもダメなのだろうか……。
「そうだ。俺達だけで考えるよか、理樹や真人も交えて提案すべきじゃないのか? 後、鈴だ。貴重な女性としての意見が聞けるかもしれないぞ? 毛利元就も言ったじゃないか。“三人寄れば文殊の知恵”ってな」
「……恭介。一ついいか?」
「ん? あぁ、どうぞお構いなく」
恭介の許可を得て、俺は思ったことをありのままに話す。
「俺は思うんだが、真人に言っても「筋トレすれば良いんじゃね?」としか答えんだろうし、理樹も「古式さん、趣味とか無いの?」とか当たり前なことしか思い浮かびそうにないし、鈴に至っては「そんなもん知るか」で一蹴されるだけのように思えるんだがな」
恭介は目を瞑って、黙り込んだ。イメージしているのだろう。
「正直スマン。聞いてるとまさにその通りなような気がしてきた」
そうだろう。きっと三人を交えれば、修正不可能なほど脱線していくか、停滞してしまうんじゃないかと思ったんだ。だったら、少数精鋭。俺とお前だけの方がまだマシだろう。
「けどなぁ……俺だって似たようなもんだぞ。何も思いつかん」
「恭介。お前、結構女子にモテるじゃないか。女心についてならお手の物なんじゃないのか? 去年のバレンタインデーチョコの数を俺は覚えているぞ」
「あのなぁ、謙吾。あれはお前が『俺はチョコなんて甘ったるい洋菓子は嫌いだ』宣言してたからだろう? それが無かったら、お前の方が確実に上だ。つまり、お前の論法だと我らがリトルバスターズの中ではお前が一番女心を理解していることになる。そのお前が分からんものを何で俺が分かるんだ?」
くっ、流石は恭介。
筋が通ってるのか通ってないのか微妙な屁理屈を並べ立てるならナンバーワンだな。
「そこを何とか頼む。お前の機転で俺を助けてくれ。お前しか頼れる奴はいないんだ」
他の者に相談しようものなら、俺と古式の間柄を邪推する者が出てくるに違いない。それに噂というものは尾鰭がつくものだ。捻じ曲げられた事実を信じて、真実を追求しようとする者がいれば、古式もいい迷惑だろう。信頼でき、尚且つ、有力なアドバイスをくれるとなれば、恭介以外に思いつかなかった。
恭介は頭の後で手を組んで、ゴロンと寝っ転がりながら言う。
「んなこと言われてもなぁ。俺だって完璧じゃないんだぜ? 毎回毎回、ぽんぽんドラえもんの秘密道具みたいにアイディアが出せるわけ……――はっ! そうだ! その手があったか!」
寝っ転がったと思ったら、急に跳ね起きた。その顔は何かを思いついたように自信に満ちていた。立ち上がって、ぎっしりとコミックが詰め込まれた本棚に向かっていった。首を回し、背表紙で何かコミックを探しているようだった。
「な、何だっ!? どうした!? 一体何を思いついたっていうんだ、恭介!?」
「ドラえもんだよ、ドラえもん! そうだよ、その手があったじゃないか!」
…………はぁ? 全く意味が分からん。ドラえもんで一体何を思いついたっていうんだこの男は? 真人の筋肉万能論とこいつの思考回路だけは一生理解できん気がする。
恭介は、一冊コミックを抜き取ると、こちらを向いた。しかし、勿体つけるようにコミックは後ろ手に隠したままだった。
「謙吾、俺はたった今、古式にとって弓道の代わりになるような生き甲斐を見つけた」
「ドラえもんでか?」
「はぁ? ドラえもんと古式の生き甲斐に何の関係があるんだ? 謙吾、お前頭大丈夫か?」
正直、今のはイラっときた。
「じゃ、さっきのドラえもんは何だったんだ?」
「あー、あれはドラえもんという言葉から連想に連想を重ねた結果、アイディアを出ただけだ。実際には、ヒントのヒントのヒントぐらいにしかなってない。マジカルバナナの最初の言葉みたいなもんだ」
それはつまり、恭介が見つけたアイディアには殆ど関係ないということか。思わせぶりなことを……。
「で、何なんだ? ドラえもんからマジカルバナナのように連想して導きだしたアイディアというのは?」
「人にモノを乞うにしちゃあ、随分と横柄じゃないか? 一応、俺は年上なんだし、頼みごとの時ぐらい敬語を使ってくれよ」
正直、今のはイライラっときた。
良かったな恭介。合計3イラだ。後2イラあったら、俺の怒り(価値=5イラ)を押し売っていたところだ。
「お願いします。恭介さん」
「フッ、他ならぬ謙吾の頼みだ。いいぜ、教えてやろう。それはな……こいつだぁぁぁぁーっ!」
恭介が息巻いて、俺に見せた物。それを見て、俺は素直な感想を言った。
「……漫画か?」
「違う! いや、確かに漫画は生き甲斐に値するほど面白いものであることは明白だが、俺が言いたいことはそんなことじゃない! もっとよく見ろ!」
言われるまま、もっとよく見た。
「……少女漫画か?」
表紙を飾る少女を見て言った。しかも……いや、まぁそれは後で言及しよう。
「確かに少女漫画だが違う! もっともっとよく見ろ! 特にタイトルの辺りを重点的に!」
言われるまま、もっともっとよく見た。
「……『恋はいつだって唐突だ』」
「誰がタイトルをまんま読み上げろっつったよ!? だーもう! 俺が今から、指差すからそれをもっともっともっとよく見ろ!」
言われるまま、もっともっともっとよく見た。
「……恋?」
「そう! 恋だ! はぁ、やれやれ。謙吾、お前は時々信じられんぐらい鈍感だな」
正直、またイラっときた。
おい気をつけろよ、恭介。後、1イラで俺の怒り(価値=5イラ)がお前の脳天に下るぞ。俺の怒りは真人の場合だと袈裟切りとか横薙ぎとか唐竹割りとかいう名で売ってるんだが、お前にはチョップという名で売ってやろう。
「しかし、それでいいのか? 本当にそれは生き甲斐になるのか?」
「何を言う。P46のジェニーのセリフを見てみろ。“あの人ことが頭から離れない。あの人の笑顔を心に浮かべるだけで……きゃっ♪ ジェニー、ハッピー・トレビあ〜ん♪ あの人のことを考えるだけで、胸がドキドキするの。もう夜も眠れナイト様♪”と言ってるじゃないか」
「………………」
「何でドン引きしてんだよ!? 俺が言ってんじゃねぇよ! ジェニーが言ってんだって!」
「いや、分かってるんだが……スマン。色んな意味で引いていた」
そう、迫真の演技をしたお前とか、脳みそピンク色みたいなそのキャラクターとか、そんな少女が主人公の少女漫画を持ってるお前とか、色々な意味で……な。
「じゃあ、もういいよ、ヘーンだ! もう他のアイディア出せとか言われても考えねーかんな!」
「あぁ、いや、俺もいいと思う。よく考えたら、恋なら特別な技能も努力もいらないし、確か恋患いが元で練習に打ち込めなくなった奴もいたしな。今の古式にはそれぐらい熱中するものがあるといいと思う」
「だろ〜♪ 俺も実はこれって名案じゃないかと思ってたんだ」
すぐ機嫌が直った。本当にこいつは時々、俺より年下なんじゃないかと思わされる時がある。
「なぁ、恭介。礼というわけじゃないんだが、俺も一つお前に助言……いや、忠告しておこう」
「あん? 何だよ?」
「その少女漫画は集めない方がいいんじゃないのか? 表紙だけ見ると……ロリ漫画にしか見えん」
「馬鹿っ、違ぇーって! この『恋はいつだって唐突だ』はなぁ! ジェニーの幼少期の話から始まるんだって! 別に第二期とされる『ジェニーボンバーラブアタック編』から読んでもいいんだが、それじゃ詳しい経緯が分かんねぇだろ!? だから一巻から買い揃えてんだよ! 断じて、一巻の表紙のジェニーがロリっ娘だから買ったんじゃねぇって! 信じてくれ、謙吾! ――俺はロリじゃない!」
「あぁ、信じているとも。お前はロリじゃない。誰一人信じなかったとしても、俺だけはそう信じてやる」
「ぐぁぁぁあああああああぁぁぁぁーっ! ぜってぇ、信じてねぇよコイツゥゥゥーっ!」
恭介が頭を抱え、ゴロゴロと床を転がって悶えていた。
その後、恭介は必死にその少女漫画の良さはロリでなく、別の所にあると語っていたが、恭介がそうやって必死になればなるほど、俺はドンドン引いていった。
「恭介」
「なんだよっ、チクショー。俺がロリじゃないと信じてくれない謙吾」
こいつ意外に根に持つなぁ。まぁ、そんなことはともかくだ。
「一緒に考えてくれてありがとう。感謝している」
何だかんだ言って、こいつは面倒見がいい……俺達リトルバスターズの頼れるリーダーだった。
「気にすんなよ、俺とお前の仲だろう? けど、お前どうすんだ?」
「何が?」
「いや、古式の恋人探しだよ。恋は一人じゃないだろう? お相手はどう見繕うんだ?」
「……ふむ、それに関してはまずは古式に提案してみてからでもいいと思っている。恋をするのは古式だからなぁ。古式が嫌と言えば、如何に準備していようが、それで仕舞いだろう?」
「そうだな。困ったらまた相談しに来い。だが、今度は理樹たちも呼ぶぞ。俺もあいつ等がいた方がアイディア脳が活性化するからな」
「あぁ、いいだろう」
実際は、『古式の恋人探し』をリトルバスターズのミッションにしたいんだろう。人の恋路の手伝いまで遊びにするのは少し気が引けるが、俺だけでこなせるとは到底思えん。恭介の機転と知恵が必須であることは明白だから、この提案は退けられない。それに俺自身、それはそれでいいかとも思う。……ただ一つ懸念があるとすれば、真人の馬鹿がうっかりこのことを周りに漏らさないかだけが心配だ。
「お、もうこんな時間か。夕飯行こうぜ、謙吾」
「あぁ」
恭介に誘われるまま、共に学食へ足を向けた。
そして、いつものように皆で夕食を食べる。
「真人、お前また皿うどんか? 昨日もそれ食べてたじゃないか」
「ふっ、恭介よ。このパリパリしたお菓子感覚が良いんじゃねぇか。キッズにも受けそうだぜ」
「何か見た目、大量のベビースターラーメンの上にゲロぶっかけたみたいだな」
「んなコト言うなよ! 意識して食えなくなっちまうだろ!」
「お前なら、実際ゲロが乗ってても食えるだろ」
「んだと、鈴。味噌汁、ご飯んトコにひっくり返して猫まんまにしちまうぞ、てめぇ」
ドゴッ!
「次言ったら、蹴るからな」
「……蹴ってから言うのかよ」
いつもの日常、何も変わらない。
穏やかで、心休まる風景。
「もう二人とも喧嘩しないで食べなよ。ほら、鈴も食事中に足上げない」
「我が妹ながらはしたないな。これからは『食事中でも蹴りを入れるノーマナー娘』と呼んでやろう」
「勝手に変な呼び方すんなボケーっ!」
俺はそんな中、見つけた。
一人、誰からも忘れられたように隅で黙々と食事をする――古式みゆきの姿を。
「……言っとくがな、真人。かすめ取ったコロッケは何かで補ってもらうぞ」
「ありゃ? 余所見してっから食い放題だなと思ってたのに。流石だな、謙吾」
「とりあえず、このカツ一切れで許してやろう」
「だぁぁぁーっ! 最後の楽しみに残してたカツがぁぁぁーっ!」
「……皿うどんだけじゃ足りないんだね、真人」
「皿うどんは前菜で、カツがメインディッシュだったんだよっ! くそっ、返せよ謙吾!」
「大いに断る。一切れぐらいでギャーギャー騒ぐな」
もう一度、古式の方を見るとその姿はなかった。
彼女はいつも、ああして過ごしているのだろうか……。
そう思うと、不憫でならなかった。
To be continued...
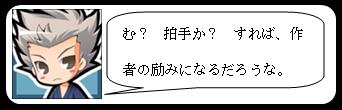
続きを見る。 別のを見る。 トップに戻る。
・感想を伝える。
掲示板
一言掲示板
メール
ぴえろの後書き
誰も見てないだろうけど、自分の物書きとしてのプライドのために再開しました。原作(虚構世界)とは展開がかなり異なってます。このSSは確かに修学旅行前のリトバスなんですが、一種の現実世界における平行世界みたいな捉え方をして下さるとありがたいです。……ややこしいっすな。もう開き直って、このSSは『ぼくがかんがえた謙吾&古式すとーりー』と言ってしまおう。キャラクターなどは崩壊しませんから、ご安心をば。(古式タソに関しては責任取れませんが)
P.S.
以前、壁紙が見にくいですというコメがありましたが、自PCで見る限りそうでもなかったのですが、確かに別のネット環境で見たら、確かに見にくかったので変更しました。
