これは、彼らが高校に入ったばかりの物語である。
筋肉馬鹿はただ笑う
written by ぴえろ
その日、偶然、剣道部が休みになり、久々に謙吾を交えて、町へ繰り出そうと理樹達は話していた。
「で? 結局、どこに行くんだよ?」
「うーん、恭介が来るまで待ってから決めよ。もうすぐLHR終わるから待ってろって、さっきメール来た」
「恭介の奴、以前メイド喫茶に行ってみたいとか言ってたが、まさかホントに行ったりしないだろうな?」
「メイド喫茶? 何だそれは? あの世へ行くのか? 新手のお化け屋敷みたいなものか?」
バタンと鈴が荒っぽく下駄箱を閉める音を耳にしながら、真人がそれに気づいた。一枚の真っ白な手紙が床に落ちていた。何気なしに拾い、裏返して「あー」と真人は声を漏らした。手紙の封は赤いハートマークのシールで留められていた。それだけでそれがどういった種の手紙であるか、すぐに察した。
「謙吾、落としたぜ」
ほい、と真人は謙吾に差し出した。リトルバスターズの中で、こういったものに縁のある人物は、恭介か謙吾だ。その手紙の表にも裏にも、差出人や宛名は書いてなかったが、二年の下駄箱で拾ったのだから謙吾宛に違いない。
謙吾は街に繰り出す時にしか履かれない、新品同然のスニーカーを履き終え、その爪先を鳴らしていたが、差し出された手紙を見て、怪訝そうに少しだけ首を傾げた。
「俺じゃないぞ?」
「知らねぇうちに落ちてたんじゃねぇの?」
「いや、下駄箱を開けた時には確かにそんな物は無かった。間違いない」
「そっか。なら、理樹だな。ヒュー、やるねぇ。この色男め」
「僕でもないよ。開けた時にそんなのあったら気付くし」
「え、じゃあ、まさか鈴か? ヒュー、やるねぇ。この猫女め」
「猫女関係ないだろっ!」
次から次に仲間へ手紙を手渡そうとしていた真人は結局、予定調和的に鈴に蹴られ、延髄に衝撃が疾った。「じゃあ、誰のなんだよ!」と真人が叫んだ辺りで別の声が答えた。
「お前じゃないのか、真人」と初めからいたかのように振舞いながら恭介は続ける。「開けてみろよ」
それに対して、比較的良識派な理樹が異議を唱えた。
「待ってよ。誰宛なのか分からない人様のラブレターなんて勝手に見たらダメでしょ」
「なら聞くが、この手紙をどうすればいい。まさか、捨てるわけにもいかないだろう?」
「いや、一応落し物なんだし、先生に渡すとかして……」
「教師に渡して、HRの時にでも『このラブレター誰のだー?』と探してもらうのか? そんなことをして名乗り出る女子がいると思うか?」
「それは……いないだろうけど」
「だろう? 教師に渡した所で小学校の修学旅行時のように、風呂の後で『このパンツ誰のだー?』みたいなことになるだけだ」
「おい、謙吾。小学校の修学旅行で『あっ! オレのパンツだ!』と叫んだオレはどう反応すればいい?」
「知るか」
割と大真面目に聞いた真人だったが、謙吾にすげなく切り捨てられた。
「中を見れば、誰宛なのか分かるだろうし。もし、この中の誰でもないのなら、こっそり戻して想い人の元に届けてやればいいだろ? 時には恋のエンジェルとして振る舞うのも、リトルバスターズの活動の一環さ」
「そんな活動、あたしは今、初めて聞いたぞ」
「おっ、そうだ。俺たち男が見たら、何かと不味いだろうから、鈴に見て貰おうぜ」
こりゃ名案だ、とばかりに恭介は子供っぽい笑みを浮かべた。
「な、何!? あたしが見るのか!?」
「まぁ、見ておけば、自分がラブレターを書く時の参考になるんじゃないのか?」
「そんなモン、永遠に書くかボケー!」
唸りを上げて鈴のハイキックが謙吾に迫るが、上体を反らして軽く躱される。
ともあれ、皆があまり真剣に考えなかったせいか、他に良い案が思い浮かばず、鈴が見ることが決まった。まるで、自分に差し出されたように強張った面持ちでしばらくラブレターを見つめていた鈴だったが、「開けるぞ」と宣告すると、赤いハートのシールを意外なほど丁寧に剥がした。彼女はいつもモンペチセットを買うとそのビニールを乱暴に引き裂いて、地面に落とす。三つ折りにされた便せんを抜き出し、文面に目を通して行く。
その時、真人は両手五指を握り締め、自らの筋肉の張り具合を確かめていた。にぎにぎ、むきり。中々良い感じである。今ならば、駅前のゲームセンターにあるパンチングマシーンの自己記録を更新できるかもしれない。オレならいつでもスタバってるぜ!と両上腕二頭筋が主張しているかのようだった。特に行き先が決まらなかったら、駅前のゲームセンターを進言してみようなどと考えていると、鈴が声を掛けてきた。
「おい、真人」
「あん? どうした? 読めねぇ漢字でも出てきたのかい、お嬢さん?」
「お前に読めて、あたしに読めない漢字があるわけないだろ」
「何だとてめぇ! 上眼瞼挙筋とか読めんのかよ!」
「そんな筋肉漢字が読めなくても、人生に問題ない」と手紙を差し出して、鈴が言う。「――お前宛てだった」
不随筋の如く、上眼瞼挙筋が勝手に全力を出した。あっけを取られて、目を丸くしたとも言える。
ラブレターによれば、その日の放課後に校舎裏で待っているとしたためられていた。可愛らしい丸文字だった。謙吾が何者かが真人を嵌めようと、女子に書かせた悪辣な罠ではないかと疑ったが、差出人――加藤静代――という名前を理樹が覚えていた。
一年C組の女子で、普通の女の子であると理樹は評した。更に鈴も合同体育で一緒になったことがあることを思い出し、接してみた所、同様に普通の女の子であると理樹の評を補強した。
しかし、謙吾は頑迷に自分の考えを転向しなかった。
「やはり、解せないな。告白するにしても、こんなムードも何もない所でするものか?」
後に同じ場所にて、古式みゆきと幾度か逢瀬を繰り返すこととなる謙吾だったが、その時は真剣にそう考えていた。校舎裏はゴミ捨て場として使用されている所だ。一応、学食の裏にあるため、屋外でも食事できるようにテーブルとベンチが設置されているが誰かが使用している所は見たことがない。真人も立って待っている。と思ったら、唐突にスクワットをし始めた。
「ロマンティック大統領である謙吾の意見は尤もだが、単に加藤静代という女子が、人目につかない所を思い浮かべたら、ここだっただけかもしれないだろ?」
「人目につかないだけなら、ここでなくとも、もっと別な場所もありそうなものだが」
「何かあったとしてもだ。もしもの時のために俺たちがこうして見守ってやってるんじゃないか。そうだろう?」
「まぁ、そうだが」
手紙の真偽を確かめるような時間はなかったため、何かあったら助けに入るという場当たり的な対処で済ますこととなった。だからこそ、こうして今、四人は物陰に隠れて真人の様子を窺っているのである。
「さぁて、どんな娘が来るのやら」
恭介に関しては単なる出歯亀根性による所が大きかった。その時、「あ、来たよ」と理樹が声を上げた。
「……本当に女だな」
「だから、さっき普通の女の子だって僕と鈴が言ったじゃない」
校舎の影から出てきたのは確かに女子だった。どこか日本人形を思わせるような黒髪のおかっぱをした少女で、清純そうだった。真人が既に来ていることに驚くと、俯き加減になる。手を胸に当てているのは動悸が激しくなったからとも取れるし、遠目からでは良く分からないが紅潮しているようにも見えた。
自分の考えが穿ち過ぎてるだけだろうか。まさか本当に? 謙吾は一瞬、己を疑ったが頭を振って邪念を払う。別段、嫉妬しているわけではない。ただあまりに不自然なのだ。クラスどころか、学校中の女子に嫌われてるとは言わないまでも、恋愛対象として真人が見られたことなど小、中、高と合わせて無かった。なのに降って湧いたかのようにラブレターが来るなど、真人を――友人を嵌めようとしてる者がいるとしか、謙吾には考えられなかった。
「いや、まだ分からんぞ。あれは美人局の類かもしれん」
実際、加藤静代は野に咲く花を思わせるような素朴だが、可愛らしい容姿をしていた。
「つつもたせ、って何だ? 胃もたれの親戚みたいなもんか?」
「まぁ、そんな感じだな」
「いやいや、全然違うでしょ」
「シッ! 理樹、ちょっと黙ってろ。隠れてんのがバレる」
慌てて口を閉じる理樹だったが、どうせこの距離じゃ聞こえないんじゃないかなと、ふと疑問に思った。真人と加藤静代が接近し、何か言葉を交わしている。加藤静代の方はモジモジと手をこまねいているが、真人は綽然としている。興味無いが故の余裕のように見える。そんな真人の態度が伝わったのか、はっきり真人が言葉として伝えたのかは分からない。加藤静代はショックを受けたように目を見開き、一歩後ずさった。
「断ったな」
「断ったね」
加藤静代は顔を覆い、肩を震わせ始めた。
「泣かしたぞ」
「泣かしたな」
あたふたと慌て始めた真人が、加藤静代の肩をポンポンと叩いた。
「慰めてるな」
「セクハラだな」
「それは酷いよ、鈴」
あんまりな言い様に理樹が擁護。すると加藤静代は真人に体当たりをかました。実際には抱きついたのだが、小柄な彼女がそうすると真人の鳩尾に頭突きをかましたようにしか見えなかった。
「抱きつかれてるな」
「今度は逆セクハラか。せわしいな」
「いや、それもどうかと……」
真人がこっちに顔を向ける。困惑した表情で助けを求めていた。「謙吾、何かサインを送ってやれ」と小声で恭介が呟き、「何故、俺が」と謙吾が問い返す。「僕たちの中で、今の真人に何かしてやれるのは謙吾だけだよ!」と頼りにしているようでその実、責任を丸投げしている理樹の言葉を謙吾は都合のいいように受け止め、真人に向けてサムズアップした。真人はそれを見て、力強く頷いた。
「一体、今のサムズアップに何の意味が……」
「いや、特に意味は無い」
「無かったの!?」
「強いて言えば、頑張れという意味だな」
謙吾も丸投げだった。真人がどんな風に受け取ったかは謎だが、一度加藤静代を引き離し、何か話し始めた。加藤静代が何か言ったのだろう。真人が一瞬、「え?」と間の抜けた顔をした。腕を組んで、何か考え事をした後、頷く。加藤静代はパッと表情を明るくすると、真人に頭を下げた。真人がそれに応じると加藤静代は立ち去った。角を折れる際、もう一度頭を下げた。
そこまで見送ると、腕を組んで難しそうな顔をしたまま、真人は四人の元に戻って来た。
「どうなったんだ? 断ったように見えたが?」
恭介が表情を引き締めたまま問うた。真人は答えた。
「一回デートしてくれたら諦めるんだってさ」
デートなどしたことがない真人のために、リトルバスターズの面々はその夜集合し、如何にして、真人が恥をかかず、且つ加藤静代に諦めさせるかと意見を出し合った。成功させるためでなく、安全に不時着させることを前提とした談義は、ある種、新手のイジメとも取れるが、井ノ原真人という人となりを十二分に理解している面々にとっては、真人のイメージを下げ過ぎずに諦めさせるかを検討し合うことこそが友情だった。「まぁ、これなら、あの子がストーカーに変貌することはないだろう」と恭介がそう結論付けた点から、中々に酷い談義だったことが察せられる。
次の日曜日、携帯電話を無線機及び盗聴器化させた代物――後に鈴のメンバー集めのミッションでも使用される――を命綱とした真人のデートが開始された。待ち合わせ場所は駅前の商店街、噴水のあるベンチ。普段から無秩序な喧噪の広がる場所であるが、その日は休日ということもあって、この町にこんなに人がいたのかと思わされる程、大した喧噪ぶりだった。他のメンバーは私服を纏いその喧騒に紛れて、監視に徹していた。長身であることに加え、剣道着を常時着用する謙吾がどうにも目立ち、ネックとなるものと思われたが、幸い気配を断つ術に長けていた――何処でそんな技術を体得したか謎だが――ため、同伴の妨げにはならなかった。子供の頃、隠れ鬼で謙吾は恐ろしく強敵だったことをふと理樹は思い出した。
休日にも関わらず、制服で待ち合わせ場所に赴き、お前のことなんか毛筋も気にかけちゃいねぇのさ、とさりげなくアピールする登場をした真人だったが、加藤静代は気にすることもなく、開口一番こう言った。
『ちょっと行きたい所があるんですけど、いいですか?』
イヤホン越しにその声を捉え、リトルバスターズの面々も少し戸惑う。
大人しそうな外見からもたらされた第一印象から、てっきり主導権を真人に譲ると全員が暗黙の了解のように考えていたためだった。「いきなりご破算だな」とデート企画当初から、一番どうでも良さそうにしていた鈴が他人事のように言った。事実、他人事である。
「どうする? 真人に主導権取り返すように指示した方がいいのかな?」
「いや、いいだろ。向こうに行きたい所があるなら、願ったりだ」
「別にあの女の気の済むようにした後でも、俺達が考案したデートスポットへ向かうのもアリだと俺は思う」
「何だ意外と長くなるのか? あたしはさっさと帰って猫たちにグルーミングをしてやりたいんだが……」
どうすりゃいいんだよ? と真人が小声で訊ねて来ていたので、リーダーである恭介は「激流に身を任せろ」とアドバイスした。彼は最近、指先一つで敵を粉砕するバイオレンスな少年漫画を見たばかりだった。
後手後手に回っていた。所詮、この中で男女の付き合いなどしたことがある者は一人としていなかった。
加藤静代が先導し、真人がその後ろに尾いて行く。隣を歩くという発想がないのが、真人の無関心さの証明のようですらある。そんな様子をとてもデート中であるとは思えなかったのだろう。数名の男が加藤静代に言い寄ろうとして、背後にそびえる真人に気付いて、ある者は舌打ちして、ある者は苦笑いを浮かべて、道を開ける。そんな様子を見て、男衆は虎の威を借る狐の故事を彷彿としていた。
「何か、ある日森の中で出会ったクマさんに守ってもらってるお嬢さんみたいだな」
確かに情景的にはそちらの方が的を得ていると、男衆は頷いた。恭介に限っては、自分の妹が割と女の子らしい発想をしたことへの感動が混じっていたが。
駅から電車で隣町へ行き、バスへ乗って見も知らぬバス停で降りる。
その頃には、リトルバスターズの面々にも違和感が湧き出し始めていた。人の流れが段々と細くなっていく。いつしか、人混みに紛れての尾行が困難になり、電柱や曲がり角に身を隠すようになった。バレないためには、少し遠目に距離を置かざるを得なかった。
「やはり、あの女。何か良からぬことを企んでいるんじゃないのか?」
未だに加藤静代美人局説を捨て切れていない謙吾は、警鐘を鳴らして、皆に進言する。先入観があることは否めなかったが、先程からほとんど二人が会話をしていないことが一定の説得力を持たせていた。
「でも、真人が嵌められてるとして、あの人に何のメリットがあるっていうんだろう」
「さぁな。少なくとも、真人が恨まれるような人間じゃないことは確かだが」
「いや、きっと意味なんてない。時々、あたしも意味もなくアイツを蹴りたくなるからな」
「もし、それが真実なら真人にとって、世界は相当住みにくいな……」
住宅街を歩いている時は、そんな冗談とも本気ともつかない軽口を叩け合っていた。
『ここです』
しかし、廃工場と思しき建物を背に加藤静代が振り返る頃には、そんな暢気なことをのたまうような者は一人としていなかった。人が住む場所が拡大すればするほど、そこには必ず澱みが発生する。その廃工場はそんな町の澱みを誰かが、あるいは皆が無意識に凝縮したかのような場所だった。
窓が割れて散乱したままのガラス片、風雨に晒され赤錆びを纏うようになった鉄骨、中に何が入っているか知る者は誰もいなくなったドラム缶、今やボウフラが産卵されるためだけにある汚水の張ったヘルメット。人々から見捨てられた物の数々が、この地が無法地帯であることを言葉にせずに囁いていた。敷地の中に入っただけでそれだけの混沌が横たわっているのだから、廃工場の中はどのような魔窟と化しているのかと、想像するだけで鼻が曲がりそうですらある。
こんな所がデートスポットであるわけがない。男衆は皆一様に張り詰めた表情で黙りこくっていたし、鈴は幼い頃に還ったように柳眉をハの字にして、恭介の後ろに回り、その袖をギュっと握っていた。
「さて、鬼が出るか蛇が出るかって感じだぜ」
「鬼が出るか仏が出るか、が正しい慣用句なんだけどね」
「仏が出るとしたら、それは阿修羅に他ならんだろうな。暴力沙汰か……フッ、望む所だ」
一瞬、謙吾の脳裏に天秤が現れ、片方に剣道が秤に乗ったが、もう一方の秤に友情が乗ると、それは梃子の原理を利用した道具になり果て、剣道はあっという間に空の彼方へと消えていった。むしろ、ある意味、良い機会だった。どうせ、何事か起きたとしても、恭介が上手く隠蔽してしまうのだろうがと心の片隅で思ってはいたが。
「……帰りたい」
「何かあったら、理樹と鈴は隠れてろ。幸い、隠れる場所には困らないしな。鈴のこと、頼んだぜ」
「う、うん、分かった」
冷や汗をこめかみに浮かべて、理樹が頷いた。続いて、真人に告げる。
「真人、お前最近、女絡みの厄介事なんて起こしたないよな?」
『あぁ? んなモンねーよ! 何だ。遠回しに俺はモテるとでも言いたげだな!』
「誰もそんな話をしてねぇって。と、なればだ。原因が今にないなら、遠い過去にあるのかもな」
『……お礼参りってことか? ケッ、ガキの頃のことを未だにネチっこく根に持ってる奴がいんのかよ』
確かに真人は幼い頃、小さな暴君であり、人為的な台風といっても差し支えのない悪たれ小僧だった。強さを誇示するために、強い奴を片っ端から伸して回っていた真人は、恭介に出会うことがなければ、番町の如き影の支配者――と言うより、破壊者と言うべきか――と化していたことは疑う余地がない。
探りを入れるべく、真人が加藤静代に問いかける。
『なぁ、えらく素敵なデートスポットを紹介してもらったわけだが、ここで何すんだ? 童心に還って、秘密基地ごっこでも始めんのかい? んなワケねぇよな。流石に馬鹿なオレでもそうじゃねぇことぐれぇは分かるぜ』
真人も、既にいつものひょうきん者の顔を止め、獰猛な獣が獲物を静かに狙うような容貌になっていた。荒んだ廃工場の光景が、真人の心にかつての暗黒時代を想起させる。酷く不愉快だった。
『もう少し……待っていて下さい』
加藤静代が真人に背を向けたまま、言葉少なげに答える。
心持ち、その足は震えている気がした。暴力とは無縁そうな彼女にとって、真人の鬼気は毒以外の何物でもないに違いない。何度か怖気で鳥肌が立った左腕の肘の辺りをさすっていた。
数分間か沈黙が佇んだ後、廃工場の角から男が一人現れる。
リトルバスターズの面々と同程度の若い男だった。私服なので彼らには分からないが、同じ高校生である。しかしながら、お世辞にも普通の、という形容詞はつけられそうにないガラの悪そうな男だった。
『い、井ノ原真人!? 何でお前がこんな所に!?』
男は真人を見るとサッと顔色を蒼褪めさせた。
『チッ、やっとこさ、黒幕がお出でになすったか。女を遣って呼び出したぁ、回りくどい真似しやがって! ムカツクぜ! 喧嘩売りてぇなら、最初からそう言やぁいいだろうが!』
女を経由すれば、何の疑いもなくノコノコとついてくるだろうと侮られたことも確かに不愉快だったが、それ以上にそんな回りくどい手段を行使する相手の性格が何より、鼻持ちならなかった。こういう機会を得たいのならば、古式ゆかしく、決闘状でも下駄箱に仕込んでいればいいのだ。その方が話も簡単で分かり易い。
苛立ちを込めて、小気味よく指の骨を鳴らして、真人は男に向かって歩を進める。相手が一人であるならば、自分たちに出番はないと恭介たちは静観した。真人の強さは誰よりこの面々が理解している。念の為、仲間の存在を警戒して周囲を見渡すが、それらしき人影はない。
相手も中肉中背であることも手伝って、勝負はそんなに長引かないだろうとリトルバスターズの面々は、身内贔屓込みの見解を示していた。
『ちょ、ちょっと待て! 喧嘩って、何の事だ! 俺は知らねぇぞ!?』
しかし、あからさまに身を引いて狼狽する男を見て、どうも、話が違うようだぞということに気がつき始めた。真人も毒気の抜けたような表情で、のほほんと佇んでいる。
『こいつがお前の新しい彼氏ってことかよ!』
『はい、そうです。もう……もう、私に付きまとわないでください!』
何やら二人の世界が展開されてしまい、真人を含め、リトルバスターズの面々は完全に置いてけぼりを食っていた。そして、二人の世界の結末は、最初から破滅以外になかった。
『クソ、てめぇ覚えてろよ!』
『忘れます』
『――っ! ちくしょぉぉぉー!』
冷然と別れを告げられ、男は涙ながらに遁走した。
『あー、いや、何つーか、どうなってんだ?』
真人が当惑して、加藤静代に問いかける。すると、彼女は振り向き様に謝った。ごめんなさい! と……。隠れていたリトルバスターズの面々も、大まかな事情はおぼろげに把握しつつ、姿を現し、彼女に詳しい経緯の説明を求めるのだった。
「つまり、真人は騙されて利用されたってことだよ」
理樹が極めて端的、且つ、容赦なくまとめた。
加藤静代は中学の時は荒れており、廃工場で会ったあの不良風の男と付き合っていたが、このままでは自分が心底ダメになると思い、必死に勉強して現在のこの進学校に合格し、新たに人生をやり直すのだと決意し、過去と完全に決別したつもりだったが、あの男はそれを認めず、付き纏われていた。
何度別れを告げても納得しない男に業を煮やし、既に新しい恋人がいることにしようと彼女は思った。が、そこいらの男にその役を頼んだ所で、あの男は脅して別れさせようとするに違いなかった。ふとそんな折、あの男が一度だけ、トラウマとなった男がいる、とそう話していたのを思い出した。すなわち、それが真人である。あの男は、かつての真人の被害者の一人だった。真人の方はあの男のことはすっかり忘れていたが、そこは殴った者は忘れるが、殴られた者は忘れないという奴だ。
そして、加藤静代はあのような一芝居を打ったというわけである。それを聞いて、真人は快活に笑い飛ばした。
「――何でぇ、オレが騙されただけか!」
もっとヤバイことになってるかと思ったぜ、と額に汗を拭く仕草をして、真人はにこやかに安堵した。
「お前、それでいいのか。先行きが不安いっぱいだな」
フンと謙吾は鼻を鳴らした。未だに不満たっぷりだった。
あの後、加藤静代は涙ながらに、素直に頼っていれば良かった。馬鹿な事をしたと真人に謝っていたが、そんな風に女の涙と共に謝られては恨めるわけがないし、それすら真人の馬鹿さ加減や人の好さに付け込んでいるように見えて、正直腹に据えかねた。しかし、真人のかつての業に起因しているのも事実なので、彼女ばかりを責められるわけではないと公明正大な謙吾だからこそ、私心と理知の板挟みになっていた。しかも、当の真人ときたら、馬鹿全開で怒る様子もないので、これでは俺の方が子供じゃないかと思って、余計に腹が立つのだった。
「まぁ、もしもの時は俺たちが助けになってやればいい。そうだろう、謙吾?」
恭介が肩を叩かれ、謙吾は「そうだな」と呟き、口元を綻ばせた。何にせよ、何も起こることはなかったのだから、一件落着とすべき所である。
「何というか、ただ真人の馬鹿っぷりが証明された事件だったな」
「いやいや、だって、真人だし」
「あぁ、真人だからな」
「むしろ真人だからこそといった方がいいんじゃないか? 流石だぜ、真人!」
「あ? 何だてめぇら。所詮、筋肉は筋肉なんだから、考えることはこっちに任せて、筋肉は安心して何人も寄せ付けぬような逞しい筋肉をつけるために筋トレに励んでろってか? へっ、ありがとよ」
「こいつ勝手に納得したぞ! やっぱり馬鹿だ!」
いつものように馬鹿にしながら、しかし、そこにある空気は限りなく優しかった。
END
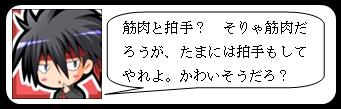
別のを見る。 トップに戻る。
・感想を伝える。
掲示板
一言掲示板
メール
ぴえろの後書き
草SSでボツった筋肉SSその1。丁度お題が「筋肉」の時に、何か淡々と且つ、サラっと読めるSSとか書いてみたかったんですよね。えりくらさんとか大谷さん的なそんな感じの。まぁ、無理でしたが。人数が多い+慣れない三人称ということで、視点がバラけちゃった感が否めない。真人は最初だけだったし、リトバスメンバー側も何か謙吾がメインかと思えば、中途半端に他のメンバーも混じってるし。統一感に欠けてます。自分だけで色々ダメ出しできるんだから、人様が見たらもっと突ける所あるだろうなぁ。直す気はないですが。
真人って、大物だと思う。大智、大愚に似たりみたいな。(あれ?逆でしたっけ?)真に強い人は誰も傷つけないように、真に賢い人って憎しみとか嫉妬とかとは無縁なのだろうなぁ。宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」をほぼ体現しているのが真人だと自分が考えてます。Keyはそういうキャラがいっぱい出てくるから好きさ! 賢く生きたって幸福になれるとは限らんよなぁ、とウルフルズを聞く度思うのさ。
